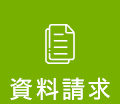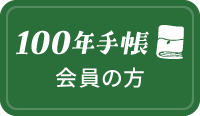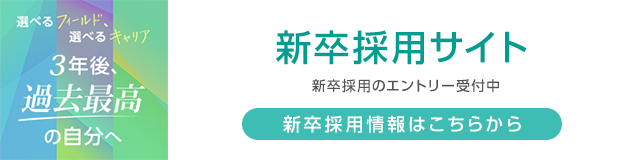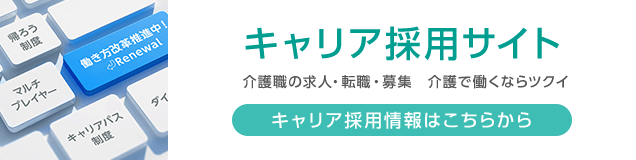介護の三原則て、なに?
「一人ひとりを尊重し、いつまでも自分らしく生活できるよう支援すること」
介護保険のサービスは
「一人ひとりを尊重し、いつまでも自分らしく生活できるよう支援すること」を目的に提供されます。
そして実現するために重要なこととして
① 生活の継続性
出来る限り在宅でそれまでと変わらない暮らしができるよう配慮する。
② 自己決定の原則
高齢者自身が生き方・暮らし方を自分で決定し、周囲はその選択を尊重する。
③ 残存能力の活用
本人ができることまで手助けするのは能力低下を招くから、やってはいけない。
が介護の三原則と言われています。

① 生活の継続性(継続)
ご入所されますと、これまで生活から一遍、生活環境が大きく変わります。お客様の心身への負担は非常に大きく、特に認知症患者の場合、症状が進行することも。少しでもこれまでの習慣や環境を変えることなく、これまでの生活の継続が大切です。
ツクイ・サンシャイン大東では集団生活でも以前と同じよう環境、生活習慣を大切に考えています。
例えば、
・使い慣れた生活用品や家具、絵や写真等の持ち込み
→使い慣れたものが部屋にある安心感の充足、
・寝る前にお風呂に入っていた→夕食後の入浴を提供
・朝はゆっくり寝ていました、夜遅くまで起きていました
→起床時間に合わせた朝食の提供
など生活習慣や生活歴に近づけた生活を提供しています。


② 自己決定の尊重(選択)
体が不自由になり、自分にできることが減っても、本人の思いが優先、本人が意思決定を優先する、というのが「自己決定の原則」です。
たとえ片麻痺になったり寝たきりになったり、認知症でも介護サービスを利用してどんな生活を送りたいのか。「○○したい」という気持ちを大切にする。
例えば
・朝はパンを食べたい、時には好きなものを食べたい
→洋食、和食の朝食選択やお茶、コーヒー等の給茶機の設置、外食レクなど
・自分の好きな服を着たい→スタッフと一緒に着替えの準備
・レクリエーションや趣味を自由に楽しみたい
→自由参加のレクリエーション、習字、カラオケ、図書館レク等趣味の充実
など日常の小さなことからご本人の希望を選択する取り組み

③ 残存能力の活用(挑戦)
何でも周囲が手伝ってしまうのではなく、今ある能力を最大限に使い、自分でできることは自分でやってもらう、出来ることを維持していただくだけでなく、
「出来る」「出来た」を感じて生活をしていただくことで生きる意欲につながります。
例えば
・普通の食事は飲み込めない、箸やスプーンが使えない
→食事形態の変更、持ちやすいスプーンやすくいやすい食器を使用
食材を乗せたスプーンをお渡しし食べていただく。
・麻痺や肢体不自由で一人で移動が出来ない
→機能訓練指導の指導、助言で残存能力を利用した移動方法の検討、
車いすや歩行器など福祉用具を活用して移動する訓練を実施
・認知機能の低下、レクリエーションで楽しめない、作業ができない
→スタッフと一緒に参加し、作業のサポートや雰囲気感じながら楽しんでいただく。
心身の状態を考慮した、個々の支援を実施、「出来た」を感じていただく取り組み

介護の三原則、我々は無意識に行っている当たり前のことですが、
介護が必要になれば選択肢が少なくなったり、出来なくなったりするのも事実です。
お客様お一人おひとりがどんな状況にあっても、当たり前の生活を送っていただけるよう
日々、サービスを提供しています。
今年は「challenge(挑戦)」「choice(選択)」「continuity(継続)」の
トリプルCを目標に掲げ、お客様と一緒に取り組みさせていただいています。