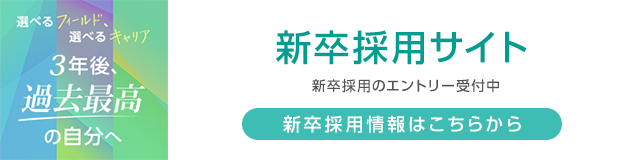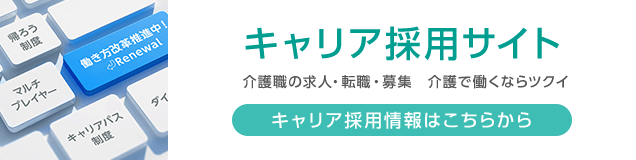高額介護サービス費
介護保険の居宅サービスや、施設サービスを利用して1カ月に支払った負担額が一定の限度額を超えた場合に、高額介護サービス費として市町村に申請することで払い戻される制度です。
【高額介護サービスの限度額】
- ※左右にスクロールすると全体がご覧いただけます
| 区分 | 負担の上限(月額) |
|---|---|
| 現役並みの所得者に 相当する方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯) |
| 世帯内のどなたかが 市町村民税を課税されている方 |
44,400円(世帯)
|
| 世帯の全員が市町村民税を 課税されていない方 |
24,600円(世帯) |
|
世帯の全員が市町村民税を 課税されていない方で 前年の合計所得金額と公的年金 収入額の合計が年間80万円 以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
- ※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計を上額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
介護保険における福祉用具貸与・販売
日常生活を住み慣れた自宅で営むことができるよう、必要な用具や、機能訓練のための用具の貸与や購入をした場合に保険給付の対象となる制度です。
国の基準を満たした指定事業者からの販売、貸与が対象となります。
指定事業者は「福祉用具貸与事業者」として指定され、専門知識のある「福祉用具専門相談員」を配置していますので、安心してサービスを受けることができます。手続きの方法や書類の様式は市区町村によって異なります。
福祉用具貸与
身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を提供できるよう、貸与を原則としています。
- ※再利用に抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは販売対象となります。
対象種目
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
- ※貸与品は介護度により借りられないもの、特別な手続きが必要なものがあります。
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売の支給限度基準額は、年間10万円の9割(9万円)までとなります。
- ※介護保険の負担割合によって負担金額が異なります。
対象種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
手続きの流れ
①ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談
②ケアマネジャーがプランを作成し、福祉用具貸与事業者を選定
③福祉用具専門相談員が被介護者に適した福祉用具を提案
④希望する福祉用具が問題なく使用できるかチェック
⑤決定したら、購入やレンタル料金を確認し契約を交わし使用開始
⑥利用者の身体状況や要介護度に合っているか福祉用具専門相談員がモニタリング
介護保険における住宅改修
住み慣れた自宅で暮らすために、手すりの取付けや段差の改修などの住宅改修費用が保険給付の対象となる制度です。
住宅改修の支給限度基準額は、20万円の9割(18万円)までとなります。
- ※1住宅につき1度の利用が限度。但し、要介護度が3段階一度に上がった際や引っ越しをした場合は再度対象となります。
- ※介護保険の負担割合によって負担金額が異なります。
住宅改修項目
対象種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続きの流れ
①ケアマネジャー等に相談
②施工事業者の選択・見積もり依頼
③市町村へ工事前に申請
④市町村は内容を確認し、結果を教示
⑤改修工事の施工 → 完成/施工業者へ支払
⑥市町村へ工事後に改修費の支給申請
⑥住宅改修費の支給額の決定・支給