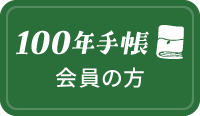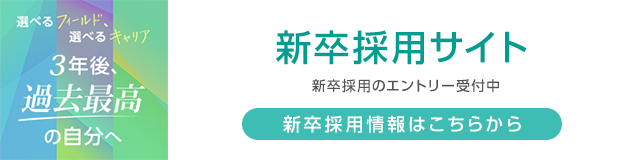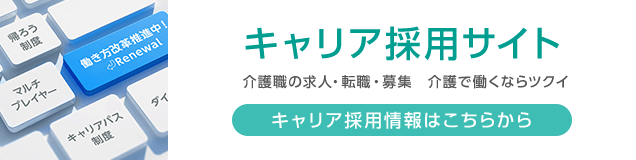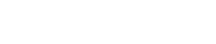2月4日は「高齢者安全入浴の日」です。毎年冬に増える入浴時の事故。入浴中に意識を失ったまま亡くなるという高齢者の不慮の事故は、厚生労働省人口動態統計(2020年)によると、高齢者の浴槽内での不慮の溺死および溺水の死亡者数は交通事故のおおよそ2倍にのぼります。冬場の入浴事故を防いで安全に入浴をするためにはどうしたらよいのか、看護師として病院に勤務後、ツクイのデイサービスや訪問入浴を経て、現在デイサービスの事業管理者をしている小林さんに話を聞きました。
冬季の入浴リスクについて
寒くなると、室温と湯温の温度差が激しくなりますので血圧の変動も大きくなります。気温の低い脱衣所や浴室に行くと、血管が縮まって血圧が上昇しますが、浴槽で体を温めると血管が広がって血圧が下がります。この血圧の急激な変動によって、場合によってはヒートショックを起こすこともありえます。夏に比べて冬は入浴中に体調不良を訴えられるケースが多いと感じます。持病がない方でも高齢者の冬の入浴は注意が必要です。
自宅で安全に入浴するために
普段過ごすリビングや居室と、浴室との温度差をなるべくおさえる対策が必要です。浴室に備え付けの暖房機能がついていれば活用しましょう。備え付けの暖房がない場合は暖房機器を持ち運んで、脱衣所・浴室全体を入浴前に温めておきましょう。浴室の床が冷たいタイルだと体を冷やします。少し熱めのシャワーをタイルにかけておくとタイルと浴室内の空気が温まります。また入浴前後には水分をとりましょう。入浴前は白湯で体を中から温めることがおすすめです。この季節ゆっくりとお風呂に入って体を温めたいところですが、長湯は避けるようにしましょう。食後すぐの入浴、特に飲酒後の入浴は危険ですので避けていただきたいです。
一人暮らしや老々介護などで温度差対策が難しい内容もあるかもしれませんが出来る対策からとっていただきたいです。

ご家族が入浴介助をされる時の注意点
ご家族から「昨日は汗だくで入浴介助をした」などお聞きする事もありますが、中には入浴介助を高齢のご家族がしているケースもあって、話を聞いていてヒヤリとする時があります。滑りやすい浴室内での入浴介助は重労働ですし危険も伴います。決して無理はしないでください。ご本人はもちろんですが、介助するご家族も体調がすぐれない時は無理をしないで体を拭くだけにする方法もあります。また転倒リスクに備え、身体のバランスが取れるように手すりを取り付ける等必要に応じて福祉用具で対策をとりましょう。ご家族がご本人を支える事が難しい場合は無理をせず、ケアマネジャーに訪問入浴サービスやデイサービスの利用を相談してみてください。
訪問入浴サービスってどんなサービス?
看護師1名と介護職員2名の3名が、専用浴槽を積んだボイラー付きの入浴車でご自宅に訪問し、居室中で防水マットの上に組み立て式の専用浴槽を設置して入浴していただくサービスです。温度変化が少ない状態で入浴していただくので入浴時の温度差が少ない事や、入浴前後の健康チェック、3名のスタッフがお客様の状態を確認しながら入浴していただくので安全性が高いサービスです。

訪問入浴サービスに抵抗がある方はどうしたらいいの?
「お風呂は自分で入りたい」そう思う方が大半だと思います。しかし中にはご自分でお風呂に入る事ができなくなり、何日も入浴できない状態が続くということもあります。過去に担当したお客様の中には、長期間お風呂に入れず髪の毛が固まってしまっていた方もいらっしゃいました。何回かサービスをご利用いただいて、ようやく髪の毛がほぐれてきて、とても喜んでくださいましたが、それまでどれほど辛かったことかと思いました。始めは訪問入浴サービスなどに、抵抗がある方は確かにいらっしゃいますが、お風呂に入ってみれば「気持ちよかった」と喜んでいただける事も少なくありません。サービス提供中はお客様とお話をしたり歌を歌ったり。心身をリフレッシュする「お風呂」という特別な空間・時間を共有させてもらえたことで、お客様と深い関係を築くことができるのではないかと思っています。「お風呂に入る」というのは人としての尊厳を守ることでもあると思います。まずは一歩踏み出して、ぜひ訪問入浴サービスを試していただきたいと思います。
現在デイサービスを利用するお客様をサポートしている小林さんは、「高齢の方にとってお風呂はすごい価値があること。」と言います。温かいお風呂でリラックスできる時間を楽しめるのも安心感があってこそです。2月4日の高齢者安全入浴の日。この機会に入浴について、またご自宅のお風呂対策について見直してみませんか。
コラム監修
小林 純平
株式会社ツクイ
通所介護事業管理者
看護師

コラム監修
小林 純平
株式会社ツクイ 通所介護事業管理者
看護師