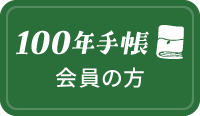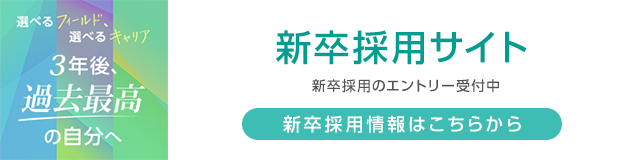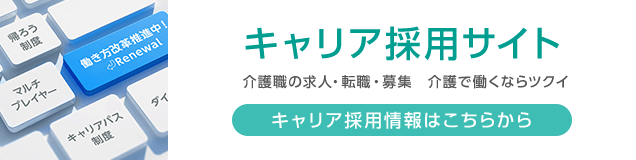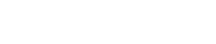約20年前は専業主婦も多く家族間での介護が主流でしたが、核家族化が進んだ現在は要介護者のいる世帯構造も大きく変わりました。2019年国民生活基礎調査によると、要介護者等がいる世帯の半数を、一人暮らしと夫婦のみ世帯で占めています。
要介護者の一人暮らしの現実と、住み替えについて株式会社ツクイ、サービス管理部の森田スペシャリストに話を聞きました。
森田さんは、介護保険制度がはじまった2000年に介護支援専門員の資格を取得して以来、これまで数多くの高齢者とそのご家族に関わってきました。森田さんによると、一人暮らしが増加した背景には、子どもに頼らず自立した生活を送りたいという高齢者も増えている一方で、親世代より先に子ども世代が要介護状態または他界、あるいは親子関係が良好でない等の理由で一人暮らしをしている方も現実には多いのだと言います。
要介護者一人暮らしの現実
高齢で要介護状態になると、身支度・掃除・洗濯・食事づくりなど日常の家事も若い頃と同じようにはいきません。家事を最低限で済ませたとしても誰からも文句を言われません。他者と積極的に関わっている方でなければ徐々に社会との繋がりも希薄になり、誰とも話さない日が続くと、次第に着替えや入浴をしなくなることもあります。一軒家にお住まいの方は「庭の手入れが出来なくなった」「2階に上れなくなった」など、自宅の管理が大変になったという話もよく聞きます。一人暮らしの期間が長かったり、要介護度が進むにつれて栄養面や清潔面など生活の質そのものが低下するケースが多いのです。また、コミュニケーションの不足から認知症の症状が進むこともあります。もちろん一人暮らしを楽しんでいる方もいますがそういった方でも、万が一の時あるいは孤独死への不安をかかえる方は少なくありません。
では「一人暮らしは避けるべきなのか」というと、決してそうではありません。
長年ケアマネジャーとして高齢者と接する中で、元気な方はマイペースでストレスが少ない方が多いと実感しています。自由でマイペースで気楽に生活ができる一人暮らしはまさにうってつけでもあるのです。食事づくりや買い物も、頭と身体へのよい運動にもなります。健康的に一人暮らしを続けるポイントについて3つにまとめました。

一人暮らしを続ける3つのポイント
「自らを律する」
睡眠や食事などリズムある生活を心がけましょう。無理をする必要はありませんが、多少大変だとしても「月曜日は庭掃除、火・金は買い物に出かける」など、自分を律してリズムある生活を送ることが大切です。
「周囲のサポートを受ける」
自分一人で難しいことが出てきたら、周囲のサポートを受けていただきたいと思います。自宅に外部の方が入ることに抵抗がある方もいますが、受け入れる勇気を持っていただきたいと思います。現実的に「出来る事」「難しいこと」を切り分けて、難しいことはケアマネジャーに対策を相談して、暮らしやすい環境を整えましょう。
「いざという時の対策を」
自宅内に一人でいるときに転倒した等何かあったときのために、ボタン一つで家族に連絡がいく緊急通報サービスを提供している自治体もあります。また、見守りサービスも各社が様々なものを用意しており、宅配や新聞配達で安否確認を兼ねるサービス等多岐にわたります。家族間で定期連絡をするなど「いつもと変わりないか」日常的に確認しておくと安心ですね。また、町内会や地域のアクティビティ、通所型サービスなど社会との繋がりがあると、いざというとき「今日〇〇さん来てないね。家に行ってみようか」など気づいてもらいやすいです。
住み替えを考えるとき
夫婦二人で暮らしている場合、どちらか一人が体調悪化したことがきっかけで、これまでの生活を維持するのが難しくなる場合があります。夫婦での生活、あるいは一人暮らしを続けるのが難しくなったとき、要介護者の身体や認知症の状態、現実にかかる費用を照らし合わせて、今後遠方の家族との同居を始めるか、施設や高齢者住宅に入居するか迷っている方も多いと思います。
住み慣れた在宅での生活を続けさせてあげたいと考えるご家族もいますし、中には仕事を辞めて介護に専念するご家族もいますが、要介護状態になってから同居を始めるのは、想像以上に大変です。これまでケアマネジャーとして多くのご家族に接してきましたが、同居をきっかけに「あんなに仲が良い家族だったのに、どうしてこんなに関係が悪くなってしまったのだろう・・」というケースを何度もみてきました。ずっと同居してきた家族が要介護状態になった場合は別ですが、介護を理由に新たに同居を始めるのは、お互いにとって大変なことです。しかも介護は自宅時間が長い方に集中する傾向があり、結果介護を担う方が疲弊してしまうことも少なくありません。特に最近では時間が自由になる18歳未満の子どもが介護を担うヤングケアラ―が社会問題にもなっていますね。
住み替えを考えるときには「こんな生活をさせてあげたい」という前に、ご本人とご家族それぞれが、どんな人生を送りたいのか「自分が最も優先したいこと」をまずは考えてほしいと思います。時には施設や高齢者住宅への入居を選択するケースもあるでしょう。そんなとき「両親が望んでいる在宅生活を続けさせてあげられなかった」と罪悪感をもつ方も多いと感じます。しかし『施設や高齢者住宅への入居=介護の終わり』ではありません。一緒に住んでいないだけで、ご家族は施設等のスタッフとともにご本人を支える介護チームの一員ですから、罪悪感を持つ必要は全くありません。それでも罪悪感をもたれる場合は、一人で抱え込まず主治医や施設等のスタッフに相談してほしいと思います。

施設や高齢者住宅への入居を成功に導く秘訣
実際には、スタッフがいる安心感や生活のしやすさに、ご本人・ご家族も「もっと早く入居すればよかった。」と言われることも多い施設や高齢者住宅での暮らし。
入居をスムーズに進めるためには、入居へのハードルを下げておく必要があります。というのも、慣れ親しんだ在宅生活からよく知らない施設生活へ変わることに不安を感じる方も多いのです。在宅から施設等の生活へスムーズに移行するためには、事前に見学に一緒に行く。良いと思った施設や高齢者住宅には何度も一緒に訪問して顔なじみのケアワーカーをつくる。あるいはショートステイを何度か活用するなど、何度も訪問することでご本人が施設に慣れてくると、入居へのハードルも下がることが多いようです。
また、費用面についても入居前によく確認しておくことが大切です。施設によって料金体系が異なり、消耗品等で思っている以上に費用がかかる場合もあります。入居後にトラブルにならないように、実際に月々どのくらいの費用がかかるのかを入居前にしっかりと確認しておきましょう。
住み替えを考えるときには、ご本人だけでなくご家族も悩むことが多いと思います。
介護を自分一人で抱え込むと苦しくなりますので、周囲のサポートを上手に借りて自分自身の生活をぜひ守ってください。自分にゆとりがあれば、ご本人にも優しく接することもできると思います。ご本人・ご家族それぞれの生活・人生を大切に、自分たちにあった「介護のかたち」を考えてください。
コラム監修
森田 恭子
株式会社ツクイ
ケアマネジャー(主任介護支援専門員)

コラム監修
森田 恭子
株式会社ツクイ
ケアマネジャー(主任介護支援専門員)