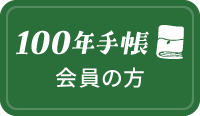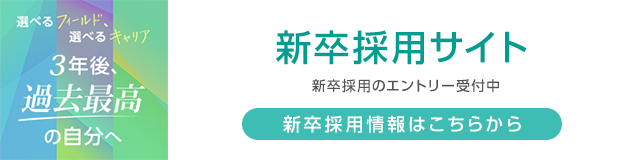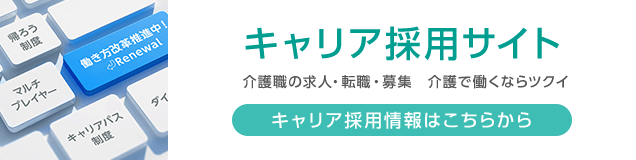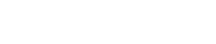「世界アルツハイマー月間」特集の後編となる今回は、「自宅にいるのに帰りたがる」「認知症の家族へのストレスで優しくなれない」をテーマにお届けします。前編に続いて、ツクイの認知症ケアコーチが介護現場で実践している対応、そしてご家族へのアドバイスをご紹介します。
CASE3 ご家族が戸惑う認知症の症状
~自宅にいるのに帰りたがる~
認知症による記憶障害や見当識障害等によって、自宅にいるにも関わらず「ここは自分の家じゃない。自分の家に帰りたい」と言う。そして毎日夕方になると「帰ります」と家を出て行こうとする。こういった症状にお悩みのご家族もいらっしゃると思います。
皆さんは、「帰りたい」と言われたとき、どのように対応してきたのでしょうか?

鈴木さん
認知症の症状で、「帰りたい」と言われる方は、その方の記憶の中でその時鮮明になっている年齢に戻っていることがあります。例えば子育て時期の記憶が鮮明だと「子どもにご飯を作らないと・・」、あるいは幼少期だと「早く帰らないとお母さんが心配する」など、「帰りたい」という気持ちの背景はその時その時によって異なります。そういった混乱している時ほど、どこに帰りたいのか、帰って何をしたいのか、その方に向き合ってゆっくりと話を聞くことを私は大切にしています。「では、一緒に帰りましょう」と一緒に外に出て、どこに何をしに帰りたいのか、何に対して不安を感じてここに居たくないのか、歩きながらたくさん話をします。
話を聴く中で、ご本人の中で、その時鮮明になっている年齢や居場所がみえてくることも多々あります。
小池さん
お客様から「帰りたい」と言われたら、「一緒に帰りましょうか」と、私もとことん一緒に歩きます。一緒に歩きながら、帰りたい理由、昔の思い出、子どもの事などたくさんお話をします。色々な話を聴く中で少しずつ心がほぐれていくこともありました。歩き疲れたころ、「そろそろお茶でも飲みませんか?」「夕食を食べませんか?」とお誘いすると「そうね」と一緒に帰ってくださることも多いです。中には、いつまでも帰ろうとされず、自力で帰れないほど遠くまで行ってしまい車で迎えに来てもらうこともありました。
坂下さん
私も同感です。その方の気持ちに寄り添って話をお聴きする。何回も繰り返すことが多い症状ですが、根気よく続けることで良い方向に向くことが多かったと思います。とはいえ中には、グループホームで「帰りたい」と言うお客様と一緒に外に出て、ご自宅とは逆側に歩き始めたはずなのに、なぜか6km離れたご自宅に着いてしまったという失敗例もありました(笑)。
~家族介護で気をつけるポイント、避けたほうがよい対応~
小池さん
人それぞれなので、認知症の症状に対しては「これが正解」という対応はないのですが「これはやらない方がいい」ということは共通していると思います。逆効果なのは、帰ろうとしている方を、止める、怒る、鍵をかけるなどです。
鈴木さん
認知症の有無にかかわらず、鍵をかけられて外に出られないとなると「閉じ込められた」と恐怖を感じると思います。閉じ込められたら何としても出たくなるもの。以前、在宅のお客様で鍵がかかって外に出られず、2階の窓から出ようとしていたケースもありました。
坂下さん
認知症は脳の病気のため、それが症状ということを理解しづらいのかもしれません。
「帰りたい」と言うのは認知症の症状です。胃が痛くて食べられないと言う人に無理やり食事を食べさせたりしないですよね。認知症の場合にも「帰る」と言う症状に対して、否定したり怒ったりしない、ということです。
鈴木さん
おすすめは、症状がいつ出るのかなどを記録にとっておくことです。記録を見返すことで、その方の傾向や対応方法がみえてくる場合もあります。そしてご本人を混乱させないように、家族間で情報共有をして、家族みんなが同じ回答を伝えられると良いと思います。
坂下さん
私たちはご本人に向き合うことが仕事ですが、何度も繰り返し「帰る」と言われるご家族はとても苦しいと思います。まずは自分たちだけで抱え込まないことを前提としていただきたいと思います。
小池さん
私も本当にそう思います。一緒に住んでいるおじいちゃん、おばあちゃんから「帰りたい」と言われたら、ご家族は「どうして?」と思うのではないでしょうか。そしてその「どうして」は、単に帰りたい理由を聞く「どうして」ではなくて、「あの元気だったお母さんが、どうしてこんな風になってしまったのだろう」という家族だからこその苦しさ、心の訴えがあることをひしひしと感じます。ですから、ご家族には決して自分たちだけで解決しようとしないで、ぜひ私たちを頼ってほしいと思います。
CASE4 ご家族が戸惑う認知症の症状
~認知症の家族介護へのストレスで優しくなれない~
『ついイライラして「こんなこともできないの?」ときつい口調で言ってしまった。大切な両親なのに、どうしても優しくなれない。私はなんてひどいことを言ってしまったのだろうか・・』多くのご家族がこのような悩みを抱えています。こういったお悩みを解消するにはどうしたらよいのでしょうか?

坂下さん
ご家族は優しくなれなくたっていいと私は思います。それはごくごく普通の感情です。同居している場合、ご家族は24時間365日ずっと関わるわけですから優しくなれなくて当たり前です。それに遠方に住んでいるご家族は、両親に会うたびに認知症の症状が進んでいく。前回出来たことが出来なくなってしまった。それを目の当たりにするのは辛いことです。優しくなれないのはご家族だからこそです。ご本人に優しくなれなくて悩んでしまう。そんな時は、大きく深呼吸をして感情を吐き出してください。そして自分を許してあげてください。
鈴木さん
職業柄、認知症の方に多く接してきましたし、プロとしての自負もあります。しかし、自分の家族となると全く別物です。認知症を理解していても、身内には優しくなれないものだとつくづく実感しています。
これまで関わらせていただいたご家族の中には、介護で何年も旅行に行けていないというご家族や、ショートステイですら罪悪感があって利用できないというご家族もいらっしゃいました。
レスパイトケアというご家族の精神的負担を減らすことを目的にショートステイを利用することも出来るので、介護で優しくなれない、余裕がないと感じたら、ぜひ旅行に行ったり好きなことをしたり自分の好きな時間を過ごしてください。
先日、何年も旅行に行っていないご家族が、ショートステイを利用して一泊旅行に行かれたので、「旅行どうでしたか?」とお聞きしました。そしたら「家にいるとイライラして怒ってしまうのに、離れてみたら何だか寂しくなっちゃった」という回答がかえってきました。また、「これを機に、半年に一度くらい旅行に行こうと思っています」というご家族の笑顔をみて、とても嬉しくなりました。介護から少し離れてみると、家族の大切さを改めて感じるものかもしれませんね。
小池さん
私たち介護に携わる者は、プロとしてさらに認知症への理解を深めていかなければならないと思います。私自身10年前とは認知症への考え方がずいぶん変わりました。これは職業として認知症の方に関わらせていただいた経験によりますが、自分が年齢を重ねることで認知症への理解が深まることもあるとつくづく感じます。介護に関わるスタッフにはもっともっと認知症に関心を持って成長してほしいと思っています。
一方で、ご家族には楽をしてほしいし、距離を置いてもいいと思います。私も経験がありますが、身内が老いることの切なさ、それを近くでずっと見続ける苦しさ。ご家族は心が持たないと思います。ですから、私たちに相談してくださるのはもちろん、苦しいときには丸投げしていただきたいのです。そして私たちはそのご家族の苦しさを、しっかりと受けとめられる介護スタッフでいたいと思っています。責任感が強い方ほど苦しい。そのようなご家族を多くみてきました。苦しい時こそ私たちに頼ってください。私たちも、介護だけでなく医療や地域など多くの方と連携しながら認知症の方お一人おひとりに向き合っていきたいと思っています。

ご家族が「抱え込まないこと」は、時には難しいかもしれません。ご本人の状態については話ができても、ご家族の悩みを話すことに抵抗がある方も中にはいるでしょう。しかし、たくさんの認知症の方のご家族と接してきた認知症ケアコーチは、異口同音に、ご家族だけで抱え込まないことの重要性を語りました。認知症介護にはご家族だけでなく多くの専門職の関わりが必要です。ご家族が心理的負担を解放することで、認知症の方とより良い関わりができるようになる場合もあります。認知症介護で悩んでいる方は、勇気を出してぜひケアマネジャーや介護スタッフに相談してみてください。
コラム監修
坂下 明美
株式会社ツクイ サービス管理課 係長
富山県認知症介護指導者、介護支援専門員、介護福祉士、認知症ケア専門士

坂下 明美
株式会社ツクイ サービス管理課 係長
富山県認知症介護指導者、介護支援専門員、介護福祉士、認知症ケア専門士

鈴木 真実
ツクイ新潟姥ヶ山グループホーム、ツクイ五泉赤海 主任所長
介護福祉士、介護支援専門員、認知症実践者研修修了、認知症実践リーダー研修修了

鈴木 真実
ツクイ新潟姥ヶ山グループホーム、ツクイ五泉赤海 主任所長
介護福祉士、介護支援専門員、認知症実践者研修修了、認知症実践リーダー研修修了

小池 晶子
ツクイ大阪菅原 所長
介護福祉士・認知症実践者研修修了・認知症ケア専門士

小池 晶子
ツクイ大阪菅原 所長
介護福祉士・認知症実践者研修修了・認知症ケア専門士