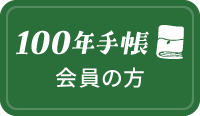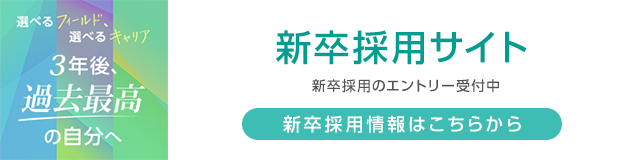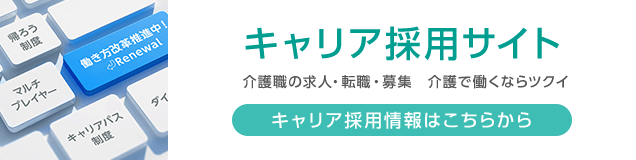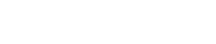ツクイの運営するシニアの「健康」「安心」「生きがい」に繋がるサービスや商品を研究・開発する研究施設ミライ想造ラボ(通称:ミラボ)で、シニア世代に向けて「災害対策と救急の勉強会」を開催しました。一年に大きな台風が何度も発生する昨今、自宅で暮らすシニア世代にとっても災害時の備えは重要です。横浜市消防局 南消防署の増田さん、松山さん、宮地さんに災害や救急時の対策や知識を教えていただきました。

高齢者を取り巻く火災事情
住宅火災による年齢別死者数の発生状況を見てみると、65歳以上の高齢者の割合が年々増加していることがわかります。更に住宅火災で亡くなった方を見ると約7割が「逃げ遅れ」が原因で亡くなっています。
横浜市の火災による年齢別死者発生状況

横浜市の住宅火災における死者発生経過(放火自殺を除く)

火災の要因は「たばこ」「ストーブ」「こんろ」など、様々ですが、高齢者の「逃げ遅れ」の理由としては判断力や体力の低下によるものが多いようです。実は逃げ遅れを防ぐアイテムがあります。「住宅用火災警報器」をご存じですか?
「住宅用火災警報器」は家電量販店やホームセンターで販売されていて、部屋の天井に簡単に取り付けることができます。

「住宅用火災警報器」は、煙や熱を感知して火災の発生を早期に感知し、警報音や音声で知らせる警報器です。設置することにより、火災による死亡のリスクを減らし、火災の早期発見にとても有効だと言われており、2004年以降すべての住宅に設置が義務付けられています。「住宅用火災警報器」を最低限設置したい場所は「寝室」「台所」「階段」の3ヵ所です。また、「住宅用火災警報器」の点検方法は「ボタンを押す」ものや「ひもを引く」など、簡単に点検できますので、年2回は点検をし、10年に一度は交換するようにしましょう。
マンションなどの集合住宅は、「自動火災報知設備」が備え付けられている場合があります。
「住宅用火災警報器」とマンションなどの天井についている「自動火災報知設備」の違いは、
「住宅用火災警報器」は、配線の必要がなく簡単に取り付けができ、警報器そのものが警報音などを出して火災発生を知らせます。 一方、「自動火災報知設備」は、配線工事によって建物全体に感知器を設置し、火災発生時に火災報知設備の受信機やベルを鳴らしたり、警備会社などに通報したりするものです。
自身の住まいを点検して、火災による逃げ遅れを防止しましょう。
救急車を呼ぶタイミング
実際に救急車を呼んだことがある人に話を聞いてみると、「具合が悪かったが、少し様子をみて我慢した。徐々に症状が悪化して最終的に救急車を呼んだ」や「救急車を呼ぶ目安がわからなかった」等の声が多く聞かれました。実際に病気やけがで救急車を呼ぶべきか迷ったときに問い合わせができる窓口があるのはご存じですか?
救急安心センター 「#7119」
救急安心センターは看護師等の専門職の方が、救急受診できる病院・診療所を教えてくれたり、今すぐに受診すべきか救急車を呼ぶべきかを電話相談できる番号です。
高齢者に多い事故と気を付ける3つのポイント
高齢者に多い救急事故は「転倒」「窒息」「溺水」の3つです。3つの事故で気を付けるポイントをご紹介しましょう。
「転倒で気をつけること」
・床に物を置かず、整理整頓する
・手すりを設置する
・電気コードを壁に沿わせるなど動線の邪魔にならないようにする
「窒息事故で気をつけること」
・餅は小さく切って食べる
・食べる前にお茶や汁物を飲み、喉を潤しておく
「溺水などお風呂の事故で気をつけること」
・入浴前に脱衣所や浴室を暖める
・浴槽から急に立ち上がらない
・食後すぐや、アルコールが抜けていない状態での入浴は控える
自然災害に備えよう
自然災害は大きく分けて「地震」「津波」「洪水」「土砂崩れ」の4つに分類することができます。
過去の大地震の大きな被害を見てみると、関東大震災は火事による焼死が9割、阪神淡路大震災では建物の倒壊や建具の転倒による窒息・圧死が7割、東日本大震災では津波による溺死が9割でした。
あらかじめ対策のできる地震による「建具の転倒防止」と「火災への備え」についてのポイントと、アイテムをご紹介します。
地震による建具の転倒防止のポイント
・背の高い家具は転倒防止器具で固定し、近くで寝る場合には、方向等に注意する
・扉、戸棚は食器等が飛び出さないよう留め金類等を取り付ける
・テレビは台に固定する
・「感震ブレーカーの設置」は大きな揺れを感じて電気を自動的に遮断する器具です。地震時の出火を大きく減らすことに有効です。


雨や風により発生する災害は、「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮による氾濫」の3種類に分けられます。
この3つの災害はハザードマップによって、危険性を事前に把握することができます。ハザードマップは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図とされています。防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどと呼ばれているものもあります。台風や大雨の自然災害は天気予報で予想することができます。まずは自分の住んでいる地域の特徴を知り、どのような災害が起こりやすい地域なのかチェックしてみましょう。

災害時には最低3日分、可能であれば7日分の備蓄があるとよいといわれています。
1年に一回は備蓄品の期限などを確認し、種類の見直しも行い、災害時に備えて安心した毎日を過ごしましょう。
お話を伺った横浜市消防局 南消防署のみなさん