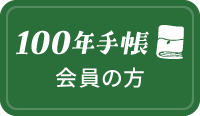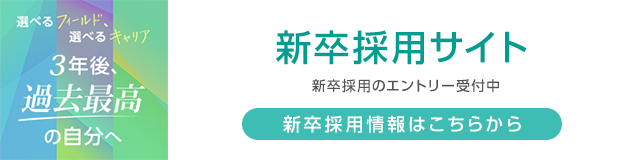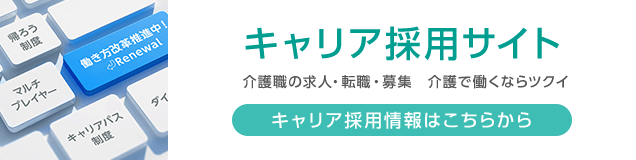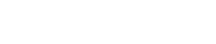訪問入浴とは?
サービス内容や費用まで
図表を使って解説!
高齢化が進む中、多くの方々が自宅での生活を希望されています。しかし、加齢や病気、障がいなどにより、自分で入浴することが難しくなるケースも少なくありません。そんなとき、訪問入浴は自宅での快適な入浴をかなえる頼もしい存在です。
ここでは、訪問入浴のサービス内容や利用方法、料金・設備・スタッフなどについて詳しく説明します。
目次
訪問入浴とはどのようなサービスですか?
訪問入浴とは、自分で入浴することが難しい方の自宅を専門のスタッフが訪問し、専用の浴槽を持ち込んで入浴をサポートするサービスです。一般的には、浴槽の設置などの準備、入浴前の健康チェック、入浴中の状態観察、身体の洗浄、入浴後の体拭きや着替えのサポートなどをおこないます。
訪問入浴ではどのような浴槽を使用するのですか?

訪問入浴では、自宅の浴槽は使用せず、専用の浴槽をスタッフが持ち込みます。浴槽が分割するタイプもあるため狭いスペースでも使用でき、安全で快適に入浴できるように設計されています。

ツクイの訪問入浴
ツクイの訪問入浴の浴槽は、寝たままの姿勢で入浴できるように設計されており、頭の脇にあるレバーを回し、ワイヤーを緩めることで、徐々に体がお湯に入っていく仕組みになっています。背丈や体重にかかわらず、どなたでもご入浴いただけます。また、医療機器メーカーが作った体重測定器もあり、入浴しながら100グラム単位で体重を測定できます。月に一度の体重測定で体調管理のサポートをしています。
訪問入浴のサービスを受ける頻度はどのくらいですか?
訪問入浴を受ける頻度は、利用者の状態や希望、介護保険の利用状況などによって異なりますが、週に1~2回が一般的です。
訪問入浴では1回につきどのくらいの時間がかかりますか?
訪問入浴にかかる時間は、利用者の状態やサービス内容によって異なりますが、準備から後片付けまで約50分が目安です。
| 準備 | 約20分 | 浴槽の設置、健康状態の確認、脱衣など |
|---|---|---|
| 入浴 | 約10分 | 浴槽へ移動介助、入浴(利用者の希望に沿った洗髪・洗顔、身体状況に合わせた洗身や全身浴、部分浴、清拭など) |
| 後片付け | 約20分 | 浴槽の片付け、着替え、健康状態の確認など |
訪問入浴はどんな人が利用できますか?
「要介護1」から「要介護5」の方の場合
主治医の入浴許可を得ている方で、自分で入浴することが難しい方が対象となります。
「要支援1」と「要支援2」の方の場合
自宅に浴室がない、感染症などの理由から他の方と共用の浴室が利用できないなど、特別な場合に限り、要支援者向けの訪問入浴の利用が可能です。
訪問入浴はどのようなスタッフがおこないますか?

訪問入浴は、基本的には看護師または准看護師の資格を持つスタッフ1名と介護スタッフ2名の合計3名でおこないます。要支援者向けの訪問入浴は介護スタッフ2名でおこなうこともあります。
訪問入浴の利用料金はどれくらいですか?
訪問入浴の利用料金は、以下の条件によって異なります。
- お住まいの地域区分
- 利用者の介護保険サービスの自己負担割合
- 加算など、その他の費用の有無
神奈川県横浜市の訪問入浴を利用した場合の1回の利用料金の目安です。
「要介護1」から「要介護5」の利用者の場合
| 自己負担割合 | 看護スタッフ1名・介護スタッフ2名でおこなう場合 |
|---|---|
| 1割 | 1,408円 |
| 2割 | 2,816円 |
| 3割 | 4,224円 |
「要支援1」と「要支援2」の利用者の場合
| 自己負担割合 | 看護スタッフ1名・介護スタッフ2名でおこなう場合 |
|---|---|
| 1割 | 952円 |
| 2割 | 1,904円 |
| 3割 | 2,856円 |
実際の利用料金については、ケアマネジャーや利用する訪問入浴の事業者にお問い合わせください。
訪問入浴の加算取得状況で算定した加算の内容により、実際の自己負担額は異なります。また、加算の適用条件は個人により異なります。
加算とは?
介護保険には、サービスの質や特定の支援に応じてさまざまな加算が存在します。加算は介護保険制度の一部であり、加算を算定するためには、サービス事業者が特定の条件や基準を満たす必要があります。以下は、訪問入浴においてよく見られる加算の一例です。
認知症専門ケア加算
認知症のある利用者に対して、専門的な支援やケアをおこなうことができる訪問入浴の事業所を利用する場合の加算です。具体的には、認知症ケアに関する専門の研修を修了した資格者を配置し、事例検討や技術的指導の会議を定期的に開催する体制を確保している訪問入浴の事業所です。
看取り連携体制加算
身体的な苦痛や、精神的な不安を抱える恐れのある、看取り期を迎える利用者とその家族に対して、主治医や訪問看護ステーションの看護スタッフなどと連携し、きめ細やかなケアを提供する体制を確保している訪問入浴の事業所を利用する場合の加算です。利用者の尊厳を守りながら穏やかな最期を支援する場合に算定されます。
訪問入浴を利用するためにはどうすればよいですか?
訪問入浴は以下のような流れで利用することができます。
| ステップ | 主な内容 |
|---|---|
| ステップ1 相談・ケアプラン作成 |
介護保険の認定を受けている利用者が訪問入浴の利用を検討する際には、まず担当のケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーが、利用者の身体的・精神的な状態や日常生活の支援が必要な程度、家族のサポート状況などを調査し、利用者のニーズに応じたケアプランを作成します。 |
| ステップ2 訪問入浴の契約 |
利用者やその家族が、ケアマネジャーのアドバイスや提案を受けて、訪問入浴の事業者と契約を結びます。 |
| ステップ3 サービスの開始 |
専門のスタッフが自宅を訪問し、訪問入浴をおこないます。 |
訪問入浴のメリットとデメリットを教えて
メリット
自宅での入浴が可能
自宅にいながら入浴できるため、施設に移動する必要がなく、安心して入浴することができます。
安全な入浴サポート
専門のスタッフが安全に配慮しながら入浴をサポートするため、転倒や事故のリスクが軽減します。
家族の負担軽減
家族が入浴の介助をする必要がなくなり、家族の介護負担が軽減されます。
健康管理
看護スタッフが訪問して健康チェックをおこなうことで、利用者の健康状態や体調の変化に気づく機会が増えます。
プライバシーの保護
自宅での入浴により、他の利用者と接触することなく、プライバシーを保つことができます。
デメリット
スペースや設備の制約
自宅のスペースや構造によっては、浴槽の設置が難しい場合があります。狭い空間やバリアフリーの対応が不十分な場合、サービスの提供に制約が生じることがあります。
サービスの頻度と時間
サービスの提供頻度や時間帯が制限される場合があります。希望する曜日や時間に利用するためには、事前に調整が必要です。
家族の立ち会いが必要な場合がある
入浴中は家族の立ち会いが必要な場合があります。これがプライバシーの問題や家族の負担になることがあります。
緊急時の対応
訪問入浴は事前に計画されたスケジュールでサービスを提供しているため、急なケアが必要となった場合には、希望する時間帯にサービスが受けられないことがあります。
これらのデメリットを理解し、サービスの利用前に十分に検討することが重要です。また、具体的なサービスの内容や契約条件について、訪問入浴の事業者に詳細に確認し、自分に合ったサービスを提供してくれる事業者を選ぶことをお勧めします。
訪問入浴についてよくある質問
集合住宅や浴室が2階の家でも入浴できますか?
訪問入浴の給湯方法には、自宅の浴室からポンプでお湯をくみ出す方法と、訪問入浴車両に搭載されたボイラでお湯を沸かして使用する方法などがあり、さまざまな住宅のタイプに対応しています。サービスを利用する前に訪問入浴の事業者やケアマネジャーにご相談ください。
家が狭いので浴槽が入るか心配です
訪問入浴は約2畳分のスペースがあれば利用できます。
準備しておくものはありますか?
訪問入浴ではバスタオル・シャンプー・石けんなどが必要ですが、事業者側が持参する場合もあります。利用者の好みのシャンプーや入浴剤などがある場合はスタッフにご相談ください。着替えは必要となりますので、ご用意ください。
部屋の中が水で漏れたり、床に傷がついたりしませんか?
訪問入浴では、スタッフが持参した防水マットを敷いて、部屋の中が水で濡れたり、床に傷がついたりしないように配慮しておこないます。心配な場合はサービス開始前にスタッフに相談することをお勧めします。
人工呼吸器などの医療機器を使っている場合はどうなりますか?
主治医の入浴許可があれば、医療機器を装着したまま入浴が可能なケースもあります。看護スタッフが入浴前に健康状態を確認し、安全を確保しながら入浴を実施します。サービス開始前にスタッフにご相談ください。
訪問入浴の際、家族は立ち会ったほうがいいのでしょうか?
利用者の身体状況を確認しながら入浴を実施しますので、可能な限り立ち会いをお願いしている訪問入浴の事業者が多いようです。

ツクイの訪問入浴
ツクイの訪問入浴は、入浴時に使用するタオル・シャンプー・ボディソープをご用意しています。入浴後の着替えだけご準備いただければ、訪問入浴をご利用いただけます。
またリラックスしてご入浴いただけるように、入浴剤も準備しています。お気に入りのタオルやシャンプーなどをご自身でご用意いただくことも可能です。
訪問入浴以外に、入浴をサポートしてくれるサービスにはどんなものがあるの?


デイサービス
多くのデイサービスでは入浴サービスが提供されており、複数のタイプの入浴設備が用意されています。入浴介助が必要な利用者には、スタッフが入浴前後の着替えや身体の洗浄をサポートします。
まとめ
訪問入浴は利用者一人ひとりの状態に応じたきめ細やかなサービスで、利用者の尊厳を守りながら、自宅で安心して入浴できるようサポートします。入浴の介助には体力が必要で、転倒などの危険も伴います。訪問入浴を利用することで、住み慣れた自宅での生活の質が向上し、家族の負担の軽減にもつながります。ぜひお近くの介護のプロに相談してみてください。